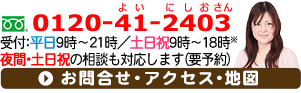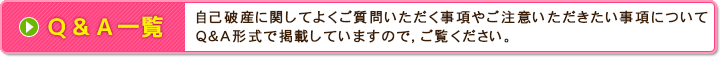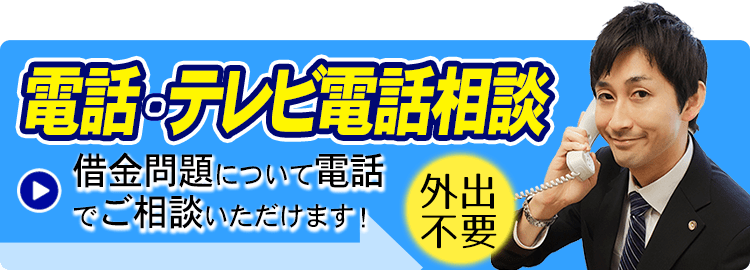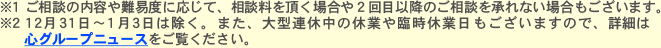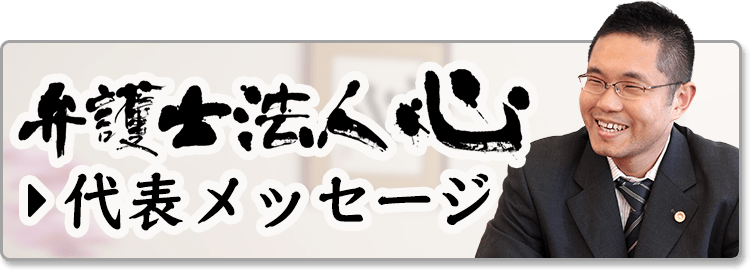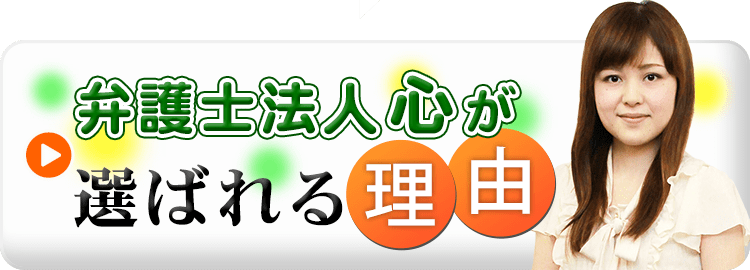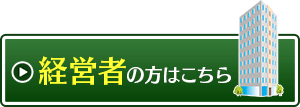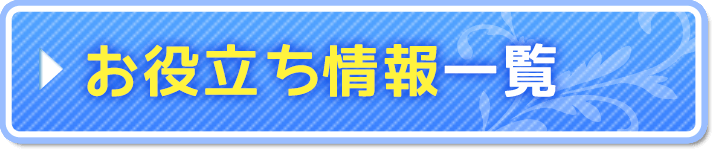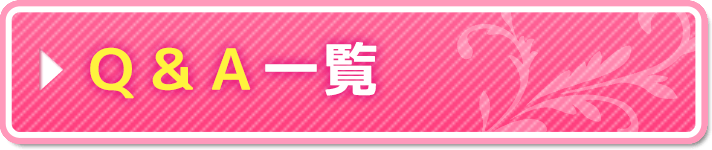お役立ち情報
自己破産で財産隠しは絶対NG|タンス貯金も調査されるのか
自己破産手続は、一部を除いた債務者の財産を処分・換価して、借金の返済に充て(配当)、残った債務(借金)については、その返済義務を免除するというものです。
申し立てをしたら単に債務がなくなるというわけではなく、所有している価値ある財産が売却され、借金の返済に充てられるのです。
しかし、破産手続をしても手元に残せる「自由財産」というものがあります。
例えば、99万円以下の現金や、生活に必要な家具・家電・生活用品等です。
そう聞くと「自己破産をしても、自分の手元にはできるだけ多く財産を残したい」と思うのは自然なことかもしれません。
そして、少しでも自分のための資産を残したいとの気持ちから、破産手続において財産を隠してしまうケースや、不当に安い金額で親族等に売却してしまうケースがあります。
このように財産を隠したり、過小申告したりした場合には、ペナルティが科せられる可能性があります。
以下、債務整理に詳しい弁護士が、破産手続における財産隠しについて説明します。
1 自己破産で財産隠しが問題となるケース
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」があります。
どちらの手続が選択されるかは、債務者の方の状況等に応じ、裁判所が決定します。
財産隠しが問題となるのは、「管財事件」となったケースです。
⑴ 管財事件
破産手続において、破産者の財産の清算等を行うのは、裁判所から選任された「破産管財人」です。
このように、破産管財人の選任される破産事件を「管財事件」と言います。
破産管財人は、破産手続開始時点の破産者の財産を管理して、処分・換価・配当等の業務を行います。
そして、その過程において、財産隠しなどの問題行為の有無を含めた、破産者の財産に関する調査を行うのです。
⑵ 同時廃止事件
他方、破産者にほとんど財産がなく、免責不許可事由(詳しくは後述)その他管財事件になるような事情がない場合には、破産管財人は選任されません。財産を清算するための破産手続は開始と同時に終了します。
このような破産事件を「同時廃止事件」と言います。
つまり、同時廃止の場合は財産が処分されることがないのです。
ただし、財産がないように見えても、債務者の方の財産に関する資料等から、申告されていない財産の存在が疑われる場合には、管財事件になることがあります。
2 財産隠しが発覚したらどうなるのか
では、もし破産者が自分の財産が換価されることを嫌がり、破産管財人に見つからないよう不正に財産を隠したり、資産を売却したりした場合、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、民事責任と刑事責任の両方が科せられる可能性があります。
同時廃止にするためにわざと財産を隠して少なく見せたり、偽装離婚による財産分与を利用したりするなど、故意的で悪質な財産隠しは絶対に行ってはいけません。
⑴ 民事責任
仮に財産を隠す行為をし、発覚した場合、「債権者を害する目的での破産者の財産を隠す行為」という免責不許可事由があるされ(破産法252条1項1号)、債務の返済責任が免除されない可能性が高いです。
例えば、以下のような事例では財産隠しにより免責不許可になる可能性があります。
- ・所有している仮想通貨の保有を申告することなく、破産管財人に対して虚偽の説明を続けたケース
- ・自己破産手続きの直前に、処分を免れるために預貯金200万円を自分の口座から家族の口座に移動させたケース
- ・経済的に破綻した状況において100万円程度の解約返戻金が見込まれる保険を破産者から妻の名義に変更したにもかかわらず、その事実を申告することなく、名義変更の事実が発覚したあとには掛捨ての保険であると虚偽の説明をしたケース
借金が免除されなければ、個人再生や任意整理等他の債務整理を検討するか、収入を増やすなどして自力で解決する他なく、債務者にとって大きな不利益となります。
⑵ 刑事責任
また、財産を隠す悪質な行為は「詐欺破産罪」という犯罪として、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、あるいは、その両方に処せられる可能性があります(破産法265条1項1号)。
このように財産の隠匿は、単に免責不許可の理由になるだけではなく、犯罪行為として厳しく処罰されることになる重大な違法行為でもあるのです。
3 財産隠しはどこまで調べられるのか
では、もし破産者が不正に財産を隠した場合、どのようにして調査がなされるかについて説明します。
⑴ 破産者に対する事情聴取
破産管財人による財産の調査は、極めて厳しく行われます。
破産管財人からの財産関係の質問に対して、破産者は十分に説明し、必要であれば追加資料等を提出しなければなりません。
これを拒否したり、曖昧・不合理な説明をすると、その行為自体が免責不許可につながる可能性もありますし、さらに客観的資料を元にした詳細な調査が行われることもあります。
⑵ 破産者の提出する財産関係の資料などから発覚
破産申立ての際には公正な清算を実現するために、破産者の保有財産を正確に申告することが非常に重要となります。
そこで、自己破産手続では、破産申立書に加えて、財産目録など、破産者の財産関係に関する多くの資料を提出しなければなりません。
例えば、提出を求められる資料は以下の通りです。
- ・保有しているすべての銀行口座の預金通帳(過去数年分)
- ・家計簿
- ・給与明細
- ・源泉徴収票
- ・不動産登記簿
- ・保険解約返戻金計算書
- ・車検証
- ・課税証明書
- ・財産の処分に関する契約書など
- ・破産者の現在保有する財産、そして過去に保有していた財産の移転に関する資料など
こうした資料には、公的機関・第三者的機関が作成・発行しているものもあります。
財産を隠している場合、何らかの痕跡が資料の中に現れることが多いので、調査によって発覚すると考えておいた方がよいでしょう。
例えば、破産申立て直前に預金口座から数十万円を出金して現金にし、タンス預金として隠したとしても、預金通帳や家計簿を調べられれば「この数十万円は何に使ったのだろう」という疑問が生じ調査の対象となります。
なお、破産管財人が選任された場合、破産者宛の郵便物は一旦すべて破産管財人に転送されます。
この制度は、債務者の方の財産調査も目的として設けられています。
クレジットカードの支払明細や、保険の支払い・更新の通知、銀行からの郵便物も転送されるので、通帳自体を隠すこと等も考えてはいけません。
4 自己破産における財産隠し行為否認の期間制限
破産管財人が財産隠しを発見した場合、破産管財人はその行為を否認することができます。
実は、この「否認権の行使」には期間の制限が設けられています。
- 【否認権の行使の時効】
-
破産手続き開始の日から2年、または債権者を害する行為の日から10年
また、財産隠しが民法424条に規定されている詐害行為取消請求権の対象になるケースもあります。
この場合の期間の制限は以下の通りです。
- 【詐害行為取消請求権の時効】
-
債務者が詐害行為をしたことを知った時から2年、または行為の日から10年
とはいえ、通常は時効よりも前に自己破産手続き中に財産隠しが発覚するでしょうから、制限期間の経過を待とうと考えるのは得策ではありません。
5 自己破産なら当法人へご相談ください
以上のとおり、法律は、財産を隠す行為に対して厳しく対処するスタンスをとっています。
破産手続における財産隠しは絶対にしてはいけません。
もし、破産手続により財産が処分されてしまうことを悩んでしまうならば、不正を犯すのではなく、何かよい解決方法を探すべきです。
当法人では、相談者様の財産状況も考慮したうえで、最適な借金問題の解決方法をご提案しております。
借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。
個人再生・任意整理など、財産を手元に残したまま行える方法も存在します。
「債務整理手続をしたいけれども、財産処分が気になってしまう」「残せるお金はいくらなのだろう」という方は、一度当法人にご相談ください。
ご相談は原則として無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
公務員が自己破産する際の注意点|職場にバレずに借金整理できるのか 自己破産のメリット・デメリット